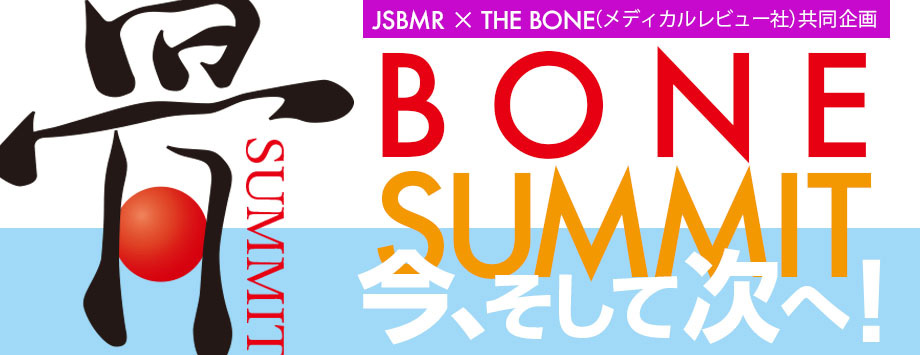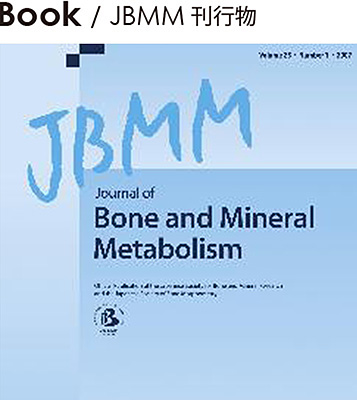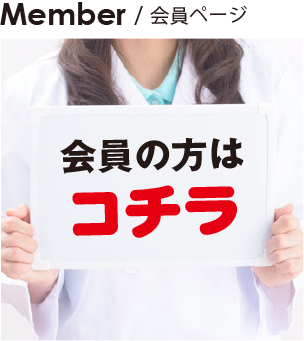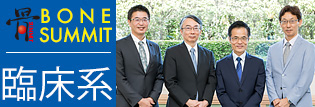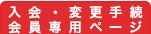
臨床系 2018年座談会
骨ミネラル代謝研究・臨床における国内外の動向
竹内 靖博 先生(虎の門病院内分泌センター センター長)
座談会メンバー
秋山 治彦 先生(岐阜大学大学院医学系研究科医科学専攻病態制御学講座 整形外科学分野 教授)
井上 大輔 先生(帝京大学医学部医学科ちば総合医療センター 第三内科学講座 教授)
萩野 浩 先生(鳥取大学医学部保健学科 教授)
医療連携 -リエゾンサービスの現状-
竹内それでは医療連携について,萩野先生、よろしくお願いします。
萩野この数年間、各地で医療連携システムの構築や、骨粗鬆症リエゾンサービス(osteoporosis liaison service:OLS)が広く認知されて、その分野で仕事をされる方も多くなっています。日本骨粗鬆症学会の取り組みにある骨粗鬆症マネージャーが2,300人程度(半分が看護師、残り半分が理学療法士と薬剤師)という規模ですが、これに限らず、二次骨折予防に取り組んでいただく方が多くなっているので、骨折を抱える患者さんが放り出されて全く治療されないという状況は、以前よりは改善しているように思います。

萩野浩先生
竹内OLSは藤田医科大学の鈴木敦詞先生らを中心に、実際の効果を検証する臨床研究が進められている状況ですが、現在、骨粗鬆症マネージャー制度が開始され、意欲のある方々が資格を取られて普及してきている状況です。今後の課題として診療報酬に反映されるようになれば最良ですが、それには時間もかかるでしょうし、資格の更新が5年で必要になるという問題もあります。何か見通しや課題への対策、それから展望というものはありますでしょうか。
萩野「二次骨折防止システムをつくると、点数の加算が得られる」、という仕組みをつくることが重要だと考えます。それができれば、医療費や介護費用が削減できることに繋がり、医療者にとっても患者さん自身にとっても、メリットが生まれるのではないでしょうか。そのためにきちんとしたデータをとって、本当にOLSが役に立つのだということを証明しなければいけません。現在、ロールモデルを作って、どういう方が取り組んでいるのかを集計しています。取り組んでおられる方々には、単に病院の収入になるということだけではなく、専門職域のみでなくプラスアルファの要素として患者さんのために役立てられるということに、大きなやりがいを感じておられます。OLSは、二次骨折予防だけでなく一次骨折予防にも取り組んでいますので、例えば町の薬剤師さんが資格を取っていただいて、骨粗鬆症の治療薬の継続に尽力していただいたり、自信を持って患者さんに説明していただいたり、教育できているわけですね。このロールモデルを骨粗鬆症マネージャーの皆さんがお互いに情報公開していくことで、大きな枠組みができれば理想的だと思います。
竹内ありがとうございます。二次骨折の予防では、治療の継続が重要になってくると思いますが、骨粗鬆症マネージャーの役割や、整形外科領域・内科領域の先生方同士の連携など、モデルケースについてご紹介いただけますでしょうか。
秋山岐阜県における取り組みとしては、大きく分けて2つあります。1つは大腿骨近位部骨折の地域連携パスに多職種で取り組んでおり、もう1つは、開業医の先生方との病診連携をどう行うかという点で、「G-KNOT」というものをつくり、大学および関連病院でホールボディDXAができる病院のリストを挙げ、岐阜市や近郊内科、泌尿器科、産婦人科などの開業医の先生方にお手紙をお送りして、骨粗鬆症の患者さんが来院されたときにホールボディDXAの扱える病院へ患者さんを紹介いただき、検査結果をまた開業医の先生方へ送るという病診連携を始めました。病院のリストを掲載するためにホームページを開設し、そこに200件以上の医療機関を掲載している状況で、一般の患者さんにもみられるようにしています。開業医の先生方にお手間をとらせないように、検査・受診の予約は大学および関連病院の地域連携室にてFAXで対応できるようにしています。患者さんは基本的には年に1~2回、大学および関連病院でホールボディDXAと腰椎・胸椎のレントゲンを撮っていただいて、その結果をもってかかりつけの開業医の先生の所へ通ってもらっています。
竹内とても理想的かつ現実的な取り組みだと思います。どのようにそのシステムを構築されていったのでしょうか?
秋山まず大学および関連病院レベルで、また同門の先生方などにお話を伺える範囲で、ホールボディDXAを扱っている病院および開業医の先生方を確認し、扱える病院には協力していただけるか連絡を取りながらリストアップしました。次に、市および県の医師会のリストをいただき、そのなかから内科、産婦人科、泌尿器科の開業医の先生方へ主にお手紙を送りまして、ホールボディDXAが必要になるような患者さんがいる場合には病診連携にご協力くださいという趣旨をお伝えし、参加の意思のある先生方にはFAXでお返事をいただいて、その後ホームページを開設しました。大学の教室のホームページのなかに「G-KNOT」というリンクをつくりまして、患者さんからもお住まいの市・町名をお調べいただくことで、「この開業医さんの所に行くと骨粗鬆症の検査と治療をしてくれますよ」という情報が得られるようにしています(https://hosp.gifu-u.ac.jp/seikei/g-knot/zenshindxa.html)。
竹内先ほど泌尿器科を挙げられたのは、前立腺癌の治療により骨折が増えるといった問題なども鑑みてのことでしょうか?
秋山泌尿器科の先生方もやはり骨粗鬆症に興味をもたれていると耳にすることが多かったため泌尿器科の先生方にも入っていただいています。
竹内どの程度の期間で一通りのシステムができあがったのでしょうか?
秋山ホームページの開設までは1年以内に完了し、その後、ポスターやパンフレットを作成し、DXAを扱っている病院や開業医の先生方にお送りしました。
こういった取り組みは各地域で行われているものだと思いますが、その地域の大学病院などが音頭を取って取り組んでいただけるのが理想的だと思います。ただ、逆紹介についてもしっかり体系立てておかないと、開業医の先生方からなかなか患者さんを紹介していただけないこともあると思います。基幹病院の内科の先生方と連携するという形も上手くいっていると耳にすることがありますので、そういった各地域の特色も鑑みた枠組みを構築することが重要なように思います。
井上そうですね。千葉県では、hip fractureの連携パスというのは一応、例えば市原市内では動いているのですが、統合的にどこかが音頭をとって統一するということは上手くいっておらず、まだまだ二次予防で消えていく患者さんたちを拾い切れていないのではないかと思います。都市部で取り組もうとすると、やはり行政の主導は欠かせないのではないかと思います。
萩野ホームページなどによって、疾患や取り組みが患者さんの前に可視化されるというのも、重要なことですね。「骨粗鬆症」や、特に「骨折」というものがあまり重大な疾患に結びつくものとして考えられていない患者さんもいますので、高齢者の方には特に「骨卒中」という言葉を浸透させることで、疾患として重要視していただくことも大切だと思います。
秋山Hip fractureについては難しいところがあり、整形外科医が、例えば人工骨頭置換術や骨折治療の後、定期的にレントゲン撮影などで経過を診させていただくと伝えますと再診していただけるのですが、高齢の方が多いためご家族が連れてこられなかったり、施設に入られると骨粗鬆症治療薬を処方していただくのは難しかったりという問題があります。そういった患者さんには、特別長期処方を認めていただくといった対応をしなければ、3ヵ月ごとに来院いただくというのはやはり限界があると思います。
おわりに
竹内重要な話題をご提供いただき、それぞれに活発にご討論いただき、誠にありがとうございました。さまざまな分野のエキスパートの先生方にお集まりいただいて、内科領域・整形外科領域それぞれにおける骨ミネラル代謝疾患の治療、骨粗鬆症と骨折に関する医療連携について、とても貴重な意見交換ができたと思います。先生方のお話が、今後の診療の展望へと繋がっていけばと思います。
本日はありがとうございました。