病因、病態から治療へ
はじめに
日本骨代謝研究会を発展させる形で第1回日本骨代謝学会が開催されたのは、1983年であった。私は1982年3月に大学を卒業したことから、私の医師、研究者としての時間は、日本骨代謝学会の歴史とほぼ重なることになる。今回、2024年度の日本骨代謝学会学術賞を受賞したことを契機に、本文の執筆を依頼された。多くの著明な諸先輩の文章と共に私の駄文が掲載されることとなるのは恐縮至極ではあるものの、少しでも日本骨代謝学会の会員の皆様、特に若い研究者の先生方の参考になればと思い、これまでに私が関わってきたきたいくつかの研究、その時点で考えていたことなどを記載させて戴きたい。ただし、かなり以前の内容も含まれており、記載が正しくない場合、あるいは、言及すべき先生すべてを記載できていないこともあるかと思われる。前もって、お詫び申し上げる。
1. 内科研修~大学院時代
私は1982年に東京大学医学部医学科を卒業、内科研修を開始した。当時は、現在のいわゆるスーパーローテート方式ではなく、内科を志望する研修医はほぼ内科のみを最長2年間研修していた。東京大学では、いくつかの内科を約6ヶ月ごとにローテートする方式がとられており、私は当時の第二内科、第四内科、および神経内科で研修を行った。尾形悦郎先生が教授を務められていた第四内科では、スタッフや研修医が四つのグループに分かれて診療を行う体制が整備されていた。私は、たまたま松本俊夫先生と同じグループの配属となった。これを契機に、松本先生にはその後長期間に渡り、大変お世話になることとなった。画像情報の認識や判読能力に長けていない私にとって、数字で判断することの多い内分泌学、特に骨・ミネラル代謝分野は、向いていたように思う。その後私は第四内科に入局し、1986年に大学院に進学、松本俊夫先生の研究室で研究を始めることとなった。(写真1)
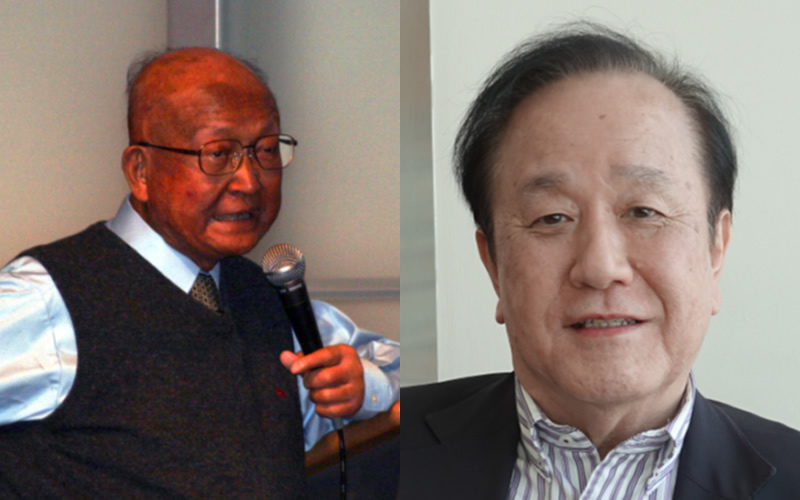
(写真1) 左)尾形 悦郎 先生(2008年11月、尾形悦郎先生の喜寿をお祝いする会にて)
右)松本 俊夫 先生(2019年9月、オーランドでのASBMR Annual Meetingにて)
当時与えられたテーマは、腫瘍随伴症候群の一つである、悪性腫瘍に伴う高カルシウム(Ca)血症の病因や病態に関する研究であった。1980年にArthur Broadus先生らのグループにより、悪性腫瘍に伴う高Ca血症は、副甲状腺ホルモン(parathyroid hormone: PTH)類似の液性因子により惹起され、尿中サイクリックAMP(cAMP)が高値を示す病態と、このような液性因子を介さず、尿中cAMPが高くない場合に大別されることが報告された(N Engl J Med 303:1377,1980)。現状で前者は、腫瘍性体液性高Ca血症(humoral hypercalcemia of malignancy: HHM)、後者は局所性骨融解性高Ca血症(local osteolytic hypercalcemia: LOH)と呼ばれている。このHHMは肺癌や腎・尿路系の固形腫瘍で、LOHは乳癌などで認められるものと考えられていた。我々は、本邦に好発する成人T細胞白血病/リンパ腫(adult T-cell leukemia/lymphoma: ATL)患者では高Ca血症が高頻度に合併することから、ATL患者のCa代謝を検討した。その結果、高Ca血症を示すATL患者は、尿中cAMPが高値であり、固形腫瘍に合併すると考えられていたHHM患者と同様の病態を示すことが明らかとなった。そこでATLの原因ウィルスであるヒトTリンパ好性ウィルス(human T-lymphotropic virus: HTLV-1)感染細胞株の培養液を用いて、このATL患者における高Ca血症惹起因子の同定を試みた。骨芽細胞様細胞株であるUMR106のcAMP産生をPTH様活性の指標として、培養液中の目的蛋白をHPLC(high performance liquid chromatography: HPLC)などを用いて精製した。ただし、培養液中にcAMP産生を促進する物質が存在すること、この物質が骨吸収も促進するであろうことを示すことはできたものの、私の実力不足のため、この物質を単一蛋白として精製、同定することはできなかった。
ちなみにこのHHM惹起因子は、いくつかのグループによる競争の結果、メルボルン大学のT John Martin先生などとGenentechのグループが、肺癌細胞株が産生する因子を精製し、そのN端アミノ酸配列に基づいて合成したオリゴヌクレオチドを使用して肺癌細胞株のcDNAライブラリーをスクリーニングするという方法により、初めて同定した(Science 237:893,1987)。PTH関連蛋白(PTH-related protein: PTHrP)と呼ばれる本蛋白のN端34個のアミノ酸の誘導体が、現在骨粗鬆症治療薬として使用されているアバロパラチドである。このPTHrPの同定に引き続き、骨・ミネラル代謝研究の分野でも、発現クローニング(expression cloning)が導入された。PTHrPに加え、本法による1991年のPTH1受容体やカルシトニン受容体、1993年のCa感知受容体(Ca-sensing receptor: CASR)などの同定により、分子生物学的手法の有用性が明確に示された。
もう一つちなみに、第四内科の松本俊夫先生の研究室には、同級の竹内靖博先生も同時に所属することとなった。同級生二人が衝突しないようにと(?)配慮戴いたためか、竹内靖博先生は虎の門病院、沖中記念成人病研究所の紫芝良昌先生のもとで、プロテオグリカンの研究を開始された。前述のPTH様活性の測定のため、当時私はHPLCで分画された各フラクションによる100 – 200サンプル中のcAMP量を測定するということを繰り返していた。一時期諸般の事情により、第四内科でのcAMP測定が不可能となることがあった。その際には、竹内靖博先生などの御尽力により、沖中記念成人病研究所でサンプルのcAMPを測定させて戴いた。これ以降も、様々な局面で竹内先生に助けて戴くこととなった。
2. オーストラリアにて
大学院修了後、メルボルン大学のT John Martin先生のもとに留学した。研究は、当時T John Martin先生が所長を務められていたSt. Vincent’s Institute of Medical Research(SVIMR)で行った。ちなみに1958年に開設されたこの研究所の初代所長は、PTHrPのN端アミノ酸配列の決定にも用いられたEdman分解で知られる、Pehr Edman先生であった。メルボルンには2年ほど滞在したが、PTHrPに関する研究には、ほとんど携わらなかった。私は主に、骨芽細胞が産生するプラズミノーゲンアクチベーターの活性調節に関する研究を行った。その過程で、生化学的手法に加え、多少の分子生物学的手法も学ぶことができた。Martin教授のもとには、当時を含め多くの日本人研究生が留学していた。私が滞在した時期にも、黒川昌栄先生、桐山健先生、池田和人先生、住谷光治先生が在籍された。これらの先生方にも、大変お世話になった。
3. 帰国後1 カルシウム代謝に関する研究
帰国後、東京厚生年金病院での勤務を経て、再度東京大学第四内科に勤務することとなった。PTHへの抵抗性を特徴とする偽性副甲状腺機能低下症患者のPTH1受容体の検討やCASRのプロモーター解析、CASR遺伝子異常による疾患の解析などを行った。これらの研究では、松本俊夫先生や竹内靖博先生に加え、池田恭治先生、岡崎亮先生、中山耕之介先生、千勝典子先生、渡邉秀美代先生、大和英之先生などの協力を戴いた。
CASRの活性型変異は、現在常染色体顕性低Ca血症1型(autosomal dominant hypocalcemia 1: ADH1)と呼ばれている病態を惹起する。本症では、通常より低い血中Ca濃度でPTH分泌が抑制されるため、PTH分泌抑制を伴う低Ca血症が惹起される。当時の第四内科の私の外来に紹介受診された低Ca血症患者の中に、生直後の発症例が2例存在した。またこれらの2症例は、通常のADH1患者とは異なり、低カリウム血症や代謝性アシドーシスなどを合併していた。これらの所見は、塩類喪失性尿細管機能異常症の一種であるバーター症候群の特徴である。既にバーター症候群の原因として、いくつかの尿細管トランスポーターやチャネルをコードする遺伝子変異が明らかにされていた。我々はこれらの患者にCASR遺伝子活性型変異が存在すること、一部の活性の高い変異CaSRが尿細管に発現するトランスポーターやチャネル活性を変化させ、バーター症候群を惹起しうることを明らかにした(Lancet 360:692,2002)。これらの症例は現在、バーター症候群5型、あるいはバーター症候群を伴う常染色体顕性低Ca血症と呼ばれている。このような症例の解析を通じ、疾患の病因から推定される通常の病態を理解し、異なる病態が存在する場合にはその理由を考えることが重要と考えている。
ちなみに、我々の報告は2002年8月31日号に掲載された。一方、J Am Soc Nephrolの2002年9月号に、フランスのグループから同様の1例が報告された(J Am Soc Nephrol 13:2259,2002)。我々はフランスグループの症例について論文発表前には承知しておらず、彼女らも同様に我々の内容については知らなかったものと思われる。異なるグループから同様の発見がほぼ同時に発表されることは、しばしば認められる。従ってこれらの論文がほぼ同時に発表されたこと、おそらく単なる偶然である。ただし2つの論文が発表されたことにより、互いの内容が速やかに確証されることとなった。
4. 帰国後2 リン代謝に関する研究
私のその後の研究内容は、一人の骨軟化症患者との出会いにより一変することとなった。腫瘍性骨軟化症(tumor-induced osteomalacia: TIO)も、腫瘍随伴症候群の一つである。本症では、責任腫瘍から産生される液性因子が腎近位尿細管リン再吸収を抑制することなどにより、慢性低リン血症、骨石灰化障害を惹起するものと考えられていた。くる病と骨軟化症は、成長軟骨帯や骨の石灰化障害を特徴とする疾患である。これらの疾患の病因は共通で、慢性低リン血症により石灰化障害が惹起される場合が多い。このうち、成長軟骨帯閉鎖以前の小児期に発症する場合をくる病と呼んでいる。我々はTIOと考えられる本患者の右大腿骨遠位部に腫瘍を発見し、この腫瘍から低リン血症惹起因子を同定することを試みた。実際、本患者の腫瘍は完全摘除でき、術後低リン血症は消失した。従って、切除した腫瘍が低リン血症を惹起していたことは確実となった。問題は、方法であった。我々が発見した腫瘍は、径約1 cm程度と小さく、骨中に存在することから一括切除(en bloc resection)は不可能で、分割切除(piecemeal resection)せざるを得なかった。さらに臨床検体であり、研究に用いることができるのは腫瘍の一部に過ぎなかった。そこで、腫瘍からのcDNAライブラリー作成を選択することとした。さらにライブラリーのスクリーニング方法も問題であった。最終的には、キリンビール株式会社の山下武美先生、島田孝志先生などとの協力のもと、腫瘍に高発現するクローンのin vivoでの作用を検討することにより、FGF23を同定した(Proc Natl Acad Sci U S A 998:6500,2001)。
ちなみに、TIO惹起腫瘍の抽出物が、フクロネズミ腎臓(opossum kidney: OK)細胞株のリン取り込みを抑制するとの成績が報告されていた(N Engl J Med 330:1645,1994)。このin vitroの実験系を用いれば、発現クローニングにより腎臓でのリン再吸収を抑制する因子を同定できる可能性があった。ただし、本アッセイは抑制活性を検出する系であること、発現クローニングの手法が確立されていたにも拘わらず、1994年以降この低リン血症惹起因子の同定がなされていなかったことから、本in vitro実験系が発現クローニングに有用かどうかは明確ではなかった。我々は、FGF23はKlotho-FGF受容体複合体に結合することにより作用を発揮することを発表している。一方、恒常的にKlothoを発現する細胞株は明らかにされておらず、現状でもFGF23のリン再吸収抑制作用を再現するin vitroの実験系は確立されていない。このことは、当然のことではあるが、用いる実験系により得られる結果が全く異なりうることを示している。
もう一つちなみに、我々の論文は2001年に公表されたが、FGF23は2000年にKenneth White先生、Michael Econs先生らにより、TIO類似の病態を示す常染色体顕性低リン血症性くる病(autosomal dominant hypophosphatemic rickets: ADHR)の原因遺伝子としてポジショナルクローニングにより同定されていた(Nat Genet 26:345,2000)(写真2)。また京都大学の伊藤先生らのグループも、同様に2000年にマウスでFgf15に対するホモロジーによりFgf23をクローニングしていた(Biochem Biophys Res Commun 277:494,2000)。このFGF23の同定も、異なるなるグループから同様の発見がほぼ同時に発表された例である。

(写真2) 2004年11月1日 アメリカ、セントルイスでのRenal Week 2004の際のFGF23に関するシンポジウムにて
左より筆者、Kenneth White先生、山下武美先生。
その後我々は、FGF23の作用や受容機構の解析、FGF23測定系の開発とリン代謝異常症患者のFGF23濃度の検討、Fgf23ノックアウトマウスの解析、リンの作用の解析などの検討を行った。これらの研究は、竹内靖博先生、田口学先生、竹田秀先生や、当時大学院生であった伊東伸朗、鈴木尚宜、清水祐一郞、新谷かおり、齋藤祐、木下佑加、堀倫子、岡本剛明諸先生、徳島大学の松本俊夫先生、井上大輔先生、遠藤逸朗先生、キリンビール株式会社の山下武美先生、島田孝志先生、山崎雄司先生、長谷川尚先生、浦川至先生、青野友紀子先生など多くの先生方の協力のもと行われた(写真3)。臨床的には、FGF23を測定できるenzyme-linked immunosorbent assay(ELISA)の開発と、本ELISAを用いたFGF23の測定の意義が大きかったと考えられる。低リン血症性くる病・骨軟化症患者の血中FGF23濃度の測定により、TIOに加え、TIOやADHR類似の病態を示し、最も頻度の高い遺伝性低リン血症性くる病の原因と考えられていたX染色体顕性低リン血症性くる病(X-linked hypophosphatemic rickets: XLH)患者でもFGF23は高値を示すことが示された。その後のXLHモデルマウスを用いた検討などにより、XLHも過剰なFGF活性により惹起される疾患と考えられるに至った。現在では、TIOやXLH、ADHRなど、10種類以上の低リン血症性くる病・骨軟化症が、過剰なFGF23活性により惹起されることが明らかにされた。これらの疾患は、本邦ではFGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症と総称されている。さらにもう一つ重要なことに、Fanconi症候群やビタミンD欠乏など、FGF23活性によらないと考えられる慢性低リン血症患者では、FGF23は低値を示した。このことは、TIOやXLH患者以外では、FGF23の産生や血中濃度がリンにより調節されていること、従ってFGF23は血中リン濃度調節に必須のホルモンであることを示唆していた。FGF23作用障害により高リン血症性疾患が惹起されること、Fgf23ノックアウトマウスやFGF23作用を阻害する抗FGF23抗体を投与された野生型マウスが高リン血症を示すことも、FGF23がリン調節ホルモンであることを示していた。

(写真3)
2011年9月 オーストラリア、ゴールドコーストでのIOF Regionals - ANZBMS Annual Scientific Meeting with JSBMRにて
左より伊東伸朗先生、筆者、清水祐一郞先生、SVIMRで知り合ったDavid Findlay先生
従来XLHなどの疾患は、低リン血症の改善を目的としてリン製剤と活性型ビタミンD製剤で治療されてきた。一方FGF23の過剰活性がXLHなどの疾患の原因で有ることが明らかにされたことから、FGF23活性の阻害がこれらの疾患の治療薬となりうると考えられた。抗FGF23抗体が、野生型マウスに加えXLHモデルマウスの血中リン濃度も上昇させたことから、ヒト抗FGF23モノクローナル抗体、ブロスマブの臨床開発が開始された。ブロスマブは、本邦では2019年にFGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症に対し保険適用となった。ブロスマブは、現在50ヶ国以上でXLHやTIO患者などに使用される薬剤となっている。
5. 徳島大学時代
上記の研究の途上、2014年に徳島大学に異動となった。徳島大学では、松本俊夫先生、沢津橋俊先生、Maria Tsoumpra先生、上甲裕大先生などとビタミンD受容体の筋肉や皮膚における作用の検討を行った(写真4)。リン代謝に関しては、髙士祐一先生、小迫英尊先生、竹本龍也先生、加藤茂明先生らと、リンがFGF受容体を介してFGF23濃度を上昇させるように作用することを明らかにした。生体がリンをどのような機構によって感知しているのかについては、現状でも議論がある。ただしリンがFGF23濃度を上昇させるように機能することは、FGF23がリン濃度調節ホルモンであることに合致している。
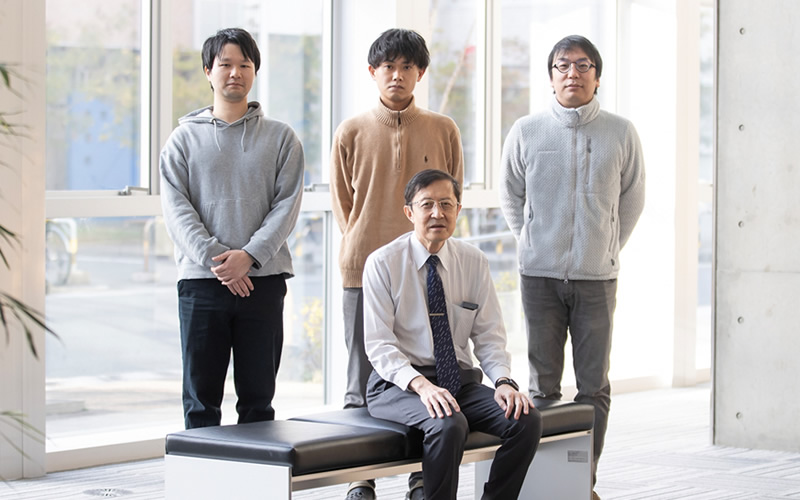
(写真4) 2023年1月 徳島大学藤井節郎記念医科学センターにて
後列左より、当時院生であった西村耕一、上甲裕大君、沢津橋俊先生
おわりに
以上、私が関わってきたいくつかの研究について、概要を記載した。振り返ってみると、基本的に私の興味は、疾患の病因や病態の解明や新たな治療法の開発にあった。基礎医学、あるいは生物学分野の先生方の興味とは、多少異なっていたように思われる。研究の過程では、いくつかの幸運に恵まれた。また、本稿で記載できなかった方も含め、多くの先生方の協力を戴いた。改めて、御礼を申し上げたい。近年骨・ミネラル代謝分野に留まらず、いわゆる稀少疾患(rare diseases)が注目されることが多くなった。この理由としては、コモンディジーズに対する主要な治療が確立されたこと、多くの稀少疾患の病因が解明されたこと、稀少疾患に対する薬剤の開発が可能であることが示されたことなど、いくつか考えられる。骨・ミネラル代謝関連の稀少疾患に対しては、アスフォターゼアルファやブロスマブ、ボソリチドなどの新薬が開発された。今後の研究により、稀少疾患を含むより多くの疾患の病因が明確にされ、病因に基づいた治療が開発されることで、現状では十分な管理が行われていない対象に対するより適切な対応が可能となることを願っている。
2025年10月30日



