心を込めて
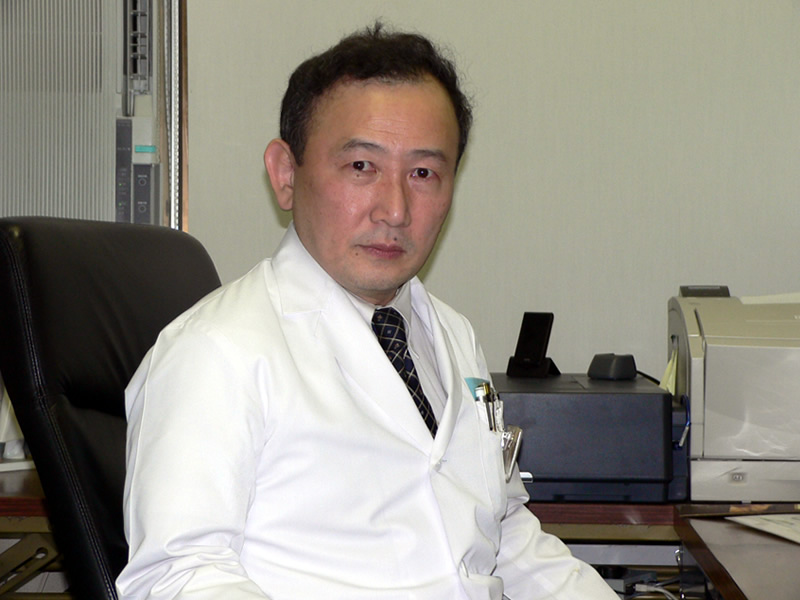
免疫をしなさい
1984年(昭和59年)に産業医科大学大学院に入学した際、第1内科学の鈴木秀郎教授のご指示にただ単に従って、内科の中でも「免疫」を専攻することになりました。東大第一内科の縮小版の講座で、どの診療科目でもよかったのですが、「免疫は将来性が最も高い分野だけど、臓器細分化が進むと出世しないリスクもある」とも言われ、NOとも言えず、研究生活が始まりました。しかし、「免疫といっても広すぎるし〜」と、研究は全くせずに診療に明け暮れていました。
1984年秋にKöhler博士とMilstein博士が、モノクローナル抗体作成技術を評価されてノーベル医学生理学賞を受賞しました。診断学や治療の画期的進歩にも繋がるはずだと記載されており、これは面白いと思って、米国NIHから帰国したばかりの免疫学の山下優毅先生の下で、全身性エリテマトーデスのBリンパ球の研究を始めました。Bリンパ球はサイトカインやMHC class II分子を介して刺激しあった結果、自発的に自己抗体を大量に産生することを見つけました。学位論文の査読者から、「リンパ球はどのようにして刺激し合うの?細胞は接着しているの?接着分子は介在するの?」などの質問が飛んできました。
「接着分子って何?面白いかも」と思い、NIHのStephen Shaw先生の研究室に留学しました。接着分子に対するモノクローナル抗体作成に1年を費やしましたが、その過程で、インテグリンは活性化して、接着構造が表に出て初めて接着できることがわかりました。また、血管内を流れるリンパ球は、ケモカインなどの刺激によってインテグリンが活性化されて、TNFなどのサイトカインの刺激で血管内皮細胞の上に発現誘導されたICAM-1やVCAM-1などの接着分子と高親和性に接着して、血管内皮細胞上に一旦停止すること、その結果、ケモカインの濃度勾配に従って組織内に遊出すること、これらが一連の接着カスケードで引き起こされることを1993年1月7日号のNatureに発表しました。リンパ球が炎症組織に集積するメカニズムが明らかになったわけです。
その際、「一連の接着カスケードをブロックすれば、リンパ球の炎症浸潤は制御できますか」との質問を何度も受けました。その質疑応答が、1993年末からの抗TNFモノクローナル抗体の敗血症への治療応用(治験は失敗)、さらに、関節リウマチへの治療応用へと繋がったと、約20年後にストックホルムでの講演の際に聞きました。1998年に米国で関節リウマチに対する抗TNF抗体インフリキシマブが承認されました。
骨もやってよ
1993年に産業医科大学第一内科に復帰した際には、江藤澄哉教授に代わっていました。江藤先生は厚生労働省の「悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症の研究」班の班長をされており、「骨もやってよ」とのご指示を戴きました。江藤先生は下関西高の先輩で、野球部の顧問でもあり、断ることは100%あり得ませんでした。小倉や銀座で息抜きに時々ご一緒しながら、骨代謝の研究を徐に始めたのでした。
正直、骨と言ってもとも思ったのですが、ヒト骨芽細胞株MG63を分けてもらって調べたところ、ICAM-1を発現し、IL-1などのサイトカインで刺激するとICAM-1の発現は増強し、VCAM-1まで発現することがわかりました。ヒトの骨髄からロイツの方法で採取した骨芽細胞ではさらに綺麗な結果でした。「これは行ける!」と思って、ヒト末梢血のTリンパ球を刺激して骨芽細胞上に振り撒くと、ベタっと接着し、抗インテグリン抗体や抗ICAM-1抗体でその接着が抑制されることが明らかになりました。さらに、Tリンパ球は接着を介して骨芽細胞にシグナルを伝えることがわかりました。
1994年(平成6年)の日本骨代謝学会でその結果を報告したところ、日本骨代謝学会奨励賞を受賞してしまい、本学会から足が抜けなくなりました。翌年にはJBMRに掲載されましたが、大御所の新潟大学小澤英浩教授、昭和大学須田立雄教授から、「現象は革新的で面白いけど、通常は骨芽細胞にリンパ球が接着している組織はあまり見ない。何を想定しているの?」との厳しいご質問を受けました。前述のようにリンパ球のインテグリンは活性化して、接着部位が表に出て初めて接着できるわけで、何らかの刺激が存在する炎症組織などを想定していると答えました。破骨細胞の前駆細胞である単球も活性化すると骨芽細胞に接着するため、炎症部での破骨細胞の分化、活性化にも細胞接着が関与することも示しました。関節リウマチでは骨びらんが早期から生じますが、そのメカニズムを明らかにしたいと思うに至りました。
骨まで愛して?
2000年(平成12年)に、江藤澄哉先生の後任として産業医科大学医学部第1内科学講座の教授を拝命しました。当時は、免疫、感染、内分泌、代謝、血液、消化器、腎を担当していたので、骨代謝研究はこれらを結びつけるには最適でした。分野横断的な骨代謝研究を始め、2003年(平成15年)には、日本骨代謝学会学術賞を受賞しましたが、リウマチ学会の偉い先生から「骨まで愛しているの?」と皮肉られました。2003年には日本でも関節リウマチに抗TNF抗体が承認され、画期的な治療効果によりパラダイムシフトの始まりと言われました。

教授就任式典(2001年1月)江藤澄哉先生、鈴木俊江様(鈴木秀郎夫人)を囲んで
関節リウマチは30-60代の女性に好発しますが、発症早期から関節破壊が始まり、一旦変形すると不可逆的です。自己反応性リンパ球が全身の関節で炎症を起こして関節の構造を壊します。根本的治療として免疫抑制薬を使い、抗リウマチ薬と呼びますが、その代表であるメトトレキサートを用いても半年以内に寛解に入らなければ、抗TNF抗体などでのバイオ抗リウマチ薬を使用します。その結果、大部分の患者で寛解が治療目標となり、寛解を維持すれば、関節破壊が進行しないことも示されました。
その後、関節リウマチに伴う関節破壊と骨粗鬆化は全く異なるメカニズムで生じることがわかりました。TNFなどの炎症性サイトカインによる刺激は、Tリンパ球や滑膜細胞にRANKL発現を誘導して骨芽細胞非依存性の破骨細胞の成熟・活性化に伴う骨破壊をもたらします。実際、滑膜が骨に接する部位に存在する破骨細胞の周囲には骨芽細胞も骨細胞も存在せず、Tリンパ球などが破骨細胞を刺激します。また、抗TNF抗体は骨粗鬆化には無効ですが、RANKLの発現抑制を介して骨破壊を制御します。さらに、抗RANKL抗体は、滑膜炎や軟骨吸収には無効ですが、骨びらん形成を完全に抑制します。斯様な病態に応じた分子標的治療薬によって、以前使用されていた合成グルココルチコイド(ステロイド薬)は殆ど不要になったはずでした。

教授回診の風景(2012年)
脱ステロイド!
合成グルココルチコイドは、1950年にノーベル賞を受賞したヘンチ博士が関節リウマチ患者に使用して以来、抗炎症作用と免疫抑制作用を期待して、自己免疫疾患など多様な疾患の治療に汎用されてきました。数え切れぬ程の生命を救い、苦痛や疼痛から解放してきた貢献度は計り知れません。しかし、分子標的治療薬が台頭し、非特異的で副作用が多いグルココルチコイドの位置付けは急激に後退し、副作用対策が真剣に論じられるようになってきました。特に、グルココルチコイドにより誘導された骨代謝異常症であるグルココルチコイド誘発性骨粗鬆症は、副作用の1/4を占め、30-50%に骨折を生じてQOLを著しく低下させます。何よりも処方した薬剤で高頻度に副作用を生ずるため、処方医には管理と治療が義務付けられるはずです。
2013年から2015年まで(平成25-27年)、日本骨代謝学会の理事長を拝命しました。在任期間中、2004年に策定したステロイド性骨粗鬆症の管理と治療のガイドラインを日本人コホートを基に改訂しました。危険因子として既存骨折、年齢、グルココルチコイド量、骨密度を抽出し、パラメータ推定値から危険因子の重み付けをして、治療介入基準を示しました。素晴らしい指針なのに、内科医への浸透は不十分でした。

第35回日本骨代謝学会(2017年7月)会長招宴(博多湾クルージング船内)

第4回日本骨免疫学会(2018年6月)万国津梁館での懇親会
その後、本疾患に対する薬剤の評価に関するエビデンスが蓄積してきました。そこで、2023年に本学会ガイドライン改訂委員会委員長として、グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症の管理と治療のガイドライン2023年版を公表しました。危険因子を有する場合、ビスホスホネート、抗RANKL抗体、テリパラチド、エルデカルシトール、またはSERMの使用が推奨されました。2023年には、幸運にも日本骨代謝学会賞を戴きました。どうもありがとうございました。
グルココルチコイドは骨代謝異常に加えて脂質、糖などの代謝異常をきたし、心血管障害などに繋がります。胃腸障害、サルコペニア等の副作用を高頻度に生じ、感染症、日和見感染症、血栓等の重篤な副作用を生じます。米国や欧州のリウマチ学会では、関節リウマチ治療においてグルココルチコイドの毒性は有益性を上回ると勧告され、全身性エリテマチーデスや血管炎のような膠原病でも、グルココルチコイドは最低限の使用に留めるか使用を回避することが推奨されています。病態を選択的に制御する分子標的治療が進歩するに従い、「脱ステロイド」の時代に変わってきています。
心を込めて
短い言葉が転機となる人生でしたが、それらを頂戴した先生をはじめ、多くの方々にご支援を賜り、心から御礼申し上げます。郷里の偉人である吉田松陰先生の銘言「至誠にして動かざる者は、未だ之有らざるなり」を胸に、教育、診療、研究など何事にも「心を込めて」を処世訓として努めてきたつもりです。押し付けたつもりはありませんが、賛同して切磋琢磨している当講座の仲間にも心から感謝しています。
2024年12月18日



