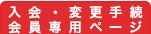
骨吸収抑制薬使用前の患者におけるARONJ発症リスクの解明;511人の後方視的検討
| 著者: | Chihiro Kanno, Momoyo Kojima, Yu Tezuka, Sadanoshin Yaginuma, Yoshiaki Kanaya, Tetsuharu Kaneko |
|---|---|
| 雑誌: | Bone. 2023 Dec:177:116892. doi: 10.1016/j.bone.2023.116892. |
- 薬剤関連顎骨壊死
- 早期発見
- 使用前抜歯

論文サマリー
ARONJは悪性腫瘍や骨粗鬆症患者に使用される骨吸収抑制薬(ARA)の有害事象であり、患者のQOLを低下させる難治性の疾患である。ARA使用患者への歯科的対応については、近年様々な指針が示されてきているが、未だ十分でない。中でも、ARA使用前の歯科治療の重要性が種々のポジションペーパーで示されているが、適切とされる歯科治療を行った患者でもARONJは発症する。
本研究では、悪性腫瘍治療に関連したARA使用前に当科で口腔管理を行った患者を対象に、その後のARONJ発症リスクを検討した。2010年1月から2020年12月の間に当科を受診した患者のうち、ARA使用前の511人を対象とした。口腔衛生処置、保存不能歯の抜歯や義歯の調整を必要に応じて行い経過観察した。
ARONJは50人(9.1%)に発症した。ARA開始前の予後不良歯の抜歯がARONJ発症に及ぼす影響を検討したところ、抜歯群では135人中24人(17.8%)が発症したのに対し、非抜歯群では376人中26人(6.9%, p=0.0002)と、抜歯群で有意に高率であった。次に、抜歯群135人の背景因子について検討したところ、抜歯前のパノラマレントゲン写真にて骨硬化像 (HR=4.189)や根尖病巣 (HR=3.161)を認める歯牙の抜歯後は、有意に高いARONJリスク因子であった。また、抜歯部位とARONJ発症部位は87.5%で一致した。さらに、抜歯からARA開始までの期間中央値はARONJ群で32日、非ARONJ群で22日 (p=0.54)と両群間に有意差を認めず、抜歯後にARA開始まで長期間待機することの有用性は認めなかった。
著者コメント
毎日の臨床の中で、ポジションペーパーで推奨された処置を行った患者においてもARONJが発症することは実感していた。他領域の知見も含めて考える中で、抜歯前から炎症性の骨代謝異常が起きている可能性を考え検討した。今後は動物モデルを用いた詳細な機序の解明に発展させたいと考えている。これまでの「抜歯さえすればARONJは発症しない」という考えから、「抜歯後こそ注意が必要」という考えにswitchし、抜歯後患者はARONJの高リスクであると認識するきっかけになればと考える。この研究結果が、より適切なリスク評価の一つのツールとなり、ARONJの早期発見、早期治療につながれば幸いである。

(福島県立医科大学 歯科口腔外科・菅野 千敬)
2023年12月25日



